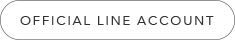- カテゴリ:
- コラム
2025年10月14日
子どもの肥満は「生活習慣病の第一歩」

◆幼児期〜思春期の肥満は、成人以降にも引き継がれる可能性が高い
現代社会で、深刻な健康問題を引き起こしている要因の一つに肥満が挙げられます。
肥満は万病の素であり、糖尿病、高血圧、動脈硬化、心不全、心筋梗塞、脂肪肝や各種がんのリスク要因になるなど、それこそ数え上げたらキリがありません。
肥満はアンチエイジング(抗老化医療)にとっても大敵であり、肥満を防ぐことが、老化を防ぐ上でも大きな予防効果を発揮することは、言うまでもないことです。
特に近年は、大人のみならず、子どもの肥満も増えており、問題になっています。
もともと、赤ちゃんはふっくらとしていて、生存戦略的に脂肪を蓄えた状態で生まれてきます。1歳頃までは、BMIの上昇が続くのは普通のことですが、立って歩き始めるとBMIも下降を始め、5〜6歳頃を境に、再び上昇を始めます。
これを、Adiposity Rebound(AR:アディポシティ・リバウンド)と言います。
このARが遅い(5〜7歳頃)子どもは、その後の肥満リスクも比較的低いとされていますが、ARが早い(2〜4歳頃)子どもは、将来的にも肥満になりやすく、各種生活習慣病にかかるリスクが高いことが明らかになっています。
幼児期に肥満だった子どもの25%は、そのまま成人肥満になると言われ、中でも思春期の肥満は70〜80%が成人肥満に移行するという調査もありますから、小さい頃の生活習慣が非常に大切だということがお分かりいただけるのではないかと思います。
《参考文献》日本小児科学会「幼児肥満ガイド」、日本小児内分泌学会HP、他
──────────────────────────────────
◆肥満と腸内細菌の意外な関係性
近年、世界的に肥満に悩む人が増えている要因として、よく言われているのがファーストフードやスナック菓子、甘いお菓子などの加工食品の氾濫や運動不足、夜ふかしなど生活リズムの乱れなどですが、それだけではありません。
実は、最近の研究によって、腸内細菌由来の構成成分や代謝物などが、宿主である人間のエネルギー代謝と密接に関わっていることが分かってきました。
腸内には、約1000種類、100兆個以上の腸内細菌がいると言われ、およそ善玉菌が2、悪玉菌が1、日和見菌が7の割合で拮抗しながら生息しています。
ところが、不規則な生活や抗生物質などがきっかけとなって、腸内細菌のバランスが崩れると、さまざまな体の不調となって現れます。
肥満の人の腸内細菌を、通常の人と調べてみると、相対的にBacteroidetes(バクテロイデス)門という種類の菌の数が少なくなっており、代わりにFirmicutes(ファーミキューテス)門の細菌が多くなっていたという研究結果があります。
実際には、細菌同士の拮抗関係や個人差等もあるため、単純にどれが善玉菌で、どれが悪玉菌だとの断定はできませんが、腸内細菌の中には、血糖値の改善や体重増加抑制などと何らかの関わりを持つものがいるのは確かなようです。
サーチュインクリニック東京
院長 高田秀実
《参考文献》
Glycative Stress Research 2019; 6 (3): 181-191、JST news April2025、他
よく読まれている記事
-
最近、明らかになってきた“腸皮膚相関”とは?
- カテゴリ:
- コラム
-
意外に知られていないメラトニンと健康の関係
- カテゴリ:
- コラム
-
病人が、病院でたらい回しにされる理由とは?
- カテゴリ:
- コラム