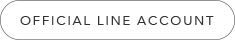- カテゴリ:
- コラム
2025年03月07日
分子栄養学の導入は、発達障害にどこまで有効か?

【分子栄養学の導入は、発達障害にどこまで有効か?】
◆最新研究で明らかになりつつある発達障害悪化の要因とは?
近年、発達障害と診断される人が急増していることに関して、注目されているのが「発達障害と栄養不足の関係」です。
最近の研究によって、発達障害や認知症の発症・悪化には、脳の栄養障害と何らかの関係があることが明らかになってきました。実際、鉄、亜鉛、ビタミンBなどを補充することで、自閉症(ASD)や注意欠如多動性障害(ADHD)患者の症状が改善したとの報告もあります。
また、腸内細菌と発達障害の関係性を指摘した研究もあります。たとえば2022年に、関西医科大学が、ASDと腸内細菌叢(腸内フローラ)の関係についての研究結果を公表しています。
これまでにも、早産児はASDの発症リスクが高いことが知られていましたが、今回、ASDの早産児と通常児の腸内フローラを比較検証した結果、大きく異なっていたことがわかったのです。
さらに、自律神経やホルモン等を介して、脳と腸は影響し合う“脳腸相関”にあることから、腸の不調と発達障害の関係性を示す調査結果も出てきています。
2023年には、京都大学や大阪大学などによる共同研究グループによって、子どもの感情制御・認知機能と腸内環境、食生活との関連性が指摘されています。
発表によると、本調査の対象となった3〜4歳児のうち、感情制御に困難を伴う子どもの腸内では、腸内炎症と関係が深いと考えられている菌叢が多く見つかったということです。
《参考文献》
関西医科大学PRESS RELEASE No.00192:2022年10月21日、京都大学:2023年9月6日、認知症治療研究会誌8巻1号(2021)、他
──────────────────────────────────
◆サーチュインクリニックでできること
現在、当サーチュインクリニックでも、予防医学の観点から、分子栄養学を取り入れた治療を行なっています。
治療を始める際は、最初に検査を行い、客観的なデータをもとに治療を進めます。例えば血液検査を行えば、体内で不足している栄養素がわかりますし、食物アレルギーなどもわかります。
腸内環境については、GI-MAPという腸内細菌検査があります。この検査を行うと、腸内細菌のバランスや栄養の消化吸収機能、腸の炎症や腸管の免疫状態などがわかります。
その他、状況に応じて、有害ミネラル検査や有機酸検査などもご用意しております。有機ミネラル検査では、体内に蓄積されている有害ミネラルを測定でき、有機酸検査では、細胞レベルの異変や栄養状態等をチェックできます。
こうした各種検査を通じて、体内の状態を詳細に把握した上で、ご希望の方には食事に関するアドバイスやサプリメントのご紹介なども行なっております。
栄養・食事療法による実際の効果について、それで急に学習障害が治るとか、対人関係がスムーズになる、といったことはありませんが、体調が安定したり、投薬量が減ったり、といった効果は期待できます。
当院では、老若男女を問わずご相談に応じております。ご自身はもちろんのこと、ご家族の気になる症状に関しても、お気軽にお問い合わせいただければと思います。
サーチュインクリニック東京 院長 高田秀実
よく読まれている記事
-
最近、明らかになってきた“腸皮膚相関”とは?
- カテゴリ:
- コラム
-
意外に知られていないメラトニンと健康の関係
- カテゴリ:
- コラム
-
病人が、病院でたらい回しにされる理由とは?
- カテゴリ:
- コラム